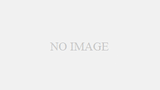「成人の日」とは、新成人を祝う日本国民の祝日です。
この「成人の日」の起源や歴史、なぜ成人式に女性は振り袖を着るようになったのかその背景など、成人の日に関する基本的な情報をご紹介します。
今年の「成人の日」はいつ?
成人の日はかつては特定の日付に固定されており、「今年の成人の日はいつ?」という疑問は生じませんでした。
しかし、現在は「ハッピーマンデー制度」により、毎年日付が変わるため、特に年始には来年のカレンダーが手元にないと成人の日がいつなのかが分かりにくい状況です。
まずは「成人の日」の日程が変わった背景と、今後の日程や対象者について詳しく見ていきましょう。
祝日法改正で、成人の日は1月の第2月曜日に
かつては1948年7月に施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に基づいて、毎年1月15日が成人の日となっていました。
しかし、現在は2000年の祝日法改正によって、成人の日は1月の第2月曜日に変更されています。
この変更の背景には「ハッピーマンデー制度」の導入があります。
この制度は、一部の祝日を月曜日に移動して連休を作り、観光やレジャー産業の振興を目指すものです。
成人の日のほかに「体育の日」(現在のスポーツの日)、「海の日」「敬老の日」もこの制度の対象となっています。
2024年(令和6年)の成人の日はいつ?対象者は?
2024年の成人の日は1月8日です。2003年4月2日から2004年4月1日生まれの人が対象者です。
元々は「年齢方式」によって、成人の日に基づいて成人を迎える年齢を決めていました。しかし、この方法では早生まれの人が同級生と一緒に成人式を祝えない問題がありました。
現在は「学齢方式」により、学年で成人式の対象者を決めることが一般的になっています。
2022年4月の法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、18歳の時期は高校3年生であり、受験や就職活動などで忙しい時期です。このため、多くの自治体では引き続き20歳を成人式の対象年齢としています。
「成人の日」の由来
古くから、子どもが一人前の大人として認められるためのさまざまな儀式が行われてきました。
これらの儀式は、時代や性別、身分に応じて異なる内容を持っており、その中には現在の成人の日の起源となったものも存在します。
これらの成人式の中で、男性と女性それぞれに特有な代表的な儀式を詳しく見ていきましょう。
男性成人式のルーツ:「元服(げんぷく)式」
かつて、公家や武家の男性が成人を迎えるために行っていた「元服式」は、現代の成人の日のルーツとされています。
「元服」は、直訳すると「頭に冠を着ける」という意味を持ちます。
この儀式では、髪型や服装を大人らしく変え、冠や烏帽子(えぼし)を頭に着けることが行われました。
元服式が行われる年齢は約15歳前後で、現代の20歳で迎える成人式よりも早い年齢で大人として認められていました。
また庶民の間でも、成人を意味する通過儀礼として、髪型の変更や褌(ふんどし)を締める行為などが行われていたそうです。
女性成人式のルーツ:「裳着(もぎ)」
公家社会での女性の成人儀式には、「裳着(もぎ)」と呼ばれるものがありました。
「裳(も)」とは、腰から下にまとう衣服を指し、成人した公家の女性がこれを身に着けるのが一般的でした。
裳着式では、女性が初めて裳を纏い、それまで垂らしていた髪を大人らしく結い上げることで成人を祝います。
この儀式は主に結婚を意識し始める年齢に行われ、多くは12歳から16歳の間に完了していました。
裳着は女性が社会的に大人として認められる重要なステップであり、その後の結婚や社会生活に大きな影響を与えていたのです。
現代の成人式の成り立ち
今日の成人式は、自治体が中心となって式典を開催し、新たな成人たちの人生の新たな門出を祝うことが一般的です。
その成人式が現在のような形になった過程を見ていきましょう。
戦後初の成人式、若者への希望のシンボル
第二次世界大戦終結後の1946年、日本で最初の成人式が埼玉県の蕨町(現・蕨市)で開催されました。
この式典は青年祭の一環として「成年式」と命名され、将来を担う若者たちを励ますと共に、新たな希望を授けることを目的としていました。
この「成年式」および青年祭は大いに好評を博し、全国的な注目を集めました。これを契機に、「成人の日」が制定され、全国各地で新成人を祝う成人式が行われるようになりました。
成人式での問題行動が注目される
成人の日には、各地で行われる成人式の様子がよくメディアで取り上げられます。
最近の報道では、会場内での騒ぎやトラブルを起こす若者たちにスポットライトが当たることが多くなっています。
これら「荒れる成人式」として知られる現象は、残念ながら以前から一部に見受けられました。
成人式に振り袖を着る理由とその意味
成人の日には、多くの女性が華やかな振り袖を身にまといます。
これは成人式の代表的な光景として多くの人に認識されている風景ですね。
では、なぜ成人式で振り袖を着るのでしょうか?
また、振り袖が女性にとってどのような意味を持つのか、その背景についても掘り下げてみましょう。
振り袖の由来と意味
振り袖は、もともと子ども用の衣服「小袖」が進化したものです。
江戸時代初期に、所作を美しく見せるために袖が長くされた振り袖が流行しました。これが現在の振り袖の起源とされています。
明治時代以降、未婚女性の正装として結納や結婚式などで着用されるようになりました。
振り袖の最大の特徴は、長い袖です。
この長い袖が、江戸時代の恋愛文化に影響を与えたと言われています。女性たちは、言葉にできない恋心を袖の振り方で伝えていました。
これが「振る」「振られる」という表現の元になっています。
結婚後は振り袖を着用しなくなり、代わりに袖の短い留袖を着るのが一般的です。そのため、現在でも振り袖は未婚女性が着る特別な衣装として位置づけられています。
振り袖の厄除けの意味
振り袖は、単なる装飾ではなく、厄除けの意味も持っています。
古くから「振る」という動作には、神様を呼び寄せる力や厄を払う力があるとされてきました。
子どもに振り袖を着せる習慣には、このような信仰が反映されていると考えられます。
特に女性の場合、19歳が初めての厄年に当たります。
成人式で振り袖を着る習慣は、このような背景から生まれたと言われています。
振り袖を着ることで「厄が去り、幸せになれるように」という願いを込める意味があるのです。
この思いが、今日まで受け継がれていると広く認識されています。