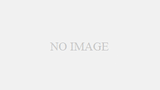お年玉をもらって喜ぶ子どもたちの顔を見ると、こっちまで嬉しくなるよね。
子どもたちにとって、お年玉をもらうのは、お金の価値を学ぶ大事な経験。
お年玉の相場を把握して、子どもの年齢に合った金額を渡すのがいいね。
お年玉の渡し方のマナーについても一緒に説明するね。

お年玉はいくらあげるべき?年齢別の気になる金額の相場
子どもの頃はお年玉をもらうのが待ち遠しかったけど、大人になって渡す側になると、いくらあげればいいのか迷うこともあるよね。
できるだけ、多すぎず少なすぎず、子どもたちが喜ぶ金額を渡したいもの。
お年玉を渡す時のポイントは、子どもが喜ぶような金額を選びつつ、親同士が気を使わない金額にすること。
適切な金額は、子どもの年齢や家族の兄弟姉妹の数、親しい度合いによって変わるんだ。
それでは、年齢別にお年玉の相場について見ていこう。
赤ちゃんや未就学児の場合
小さな子どもはまだ自分でお金を使うことが少ないから、お年玉として500円玉や1000円札を包むのはどうかな。
小さい子どもにお金を持たせたくないと思う家庭もあるので、お金は子どもではなくその親に渡す方が良い場合もあるよ。
ただ、もし年上の兄弟姉妹がいたり、親戚が集まっている場所でみんながお年玉をもらっている場合は、親の了承を得て子どもに直接渡しても大丈夫だよ。
お金の意味が分からない赤ちゃんには、現金よりも絵本やおもちゃをプレゼントすると、相手の親も喜ぶかもしれないね。
小学生の場合
お小遣いをもらい始めたり、欲しいものが出てきたりする年頃の子どもたちは、お金に対する関心が高まっているよね。小学生のお年玉の相場は、学年によって変わるよ。
低学年の子どもはまだお金の使い方が上手くないから、未就学児より少しだけ多い1000円から2000円くらいが適切な金額だよ。
3年生以上になると、自分が欲しいものがはっきりして、「お年玉でゲームを買おう」とか具体的な使い道を考えることも多くなるね。
学年にもよるけど、3000円から5000円くらいのまとまった金額を渡すのが一般的だよ。
もし小学生の兄弟姉妹がいる場合は、不公平にならないように気をつけて。金額に大きな差があると、下の子が不満を感じたり、同じ金額だと上の子がプライドを傷つけられるかもしれないからね。
年齢に500円を掛けたり、学年に1000円を掛けたりするようにお年玉の金額を決めると、みんなが納得するかもしれないよ。
中学生の場合
中学生になると、友達と出かけたりファッションに興味を持ったりすることが増えて、自分で使えるお金が欲しくなる年頃だよ。そのため、お年玉の相場は5000円から1万円となり、小学生よりも高くなることが一般的だね。
お年玉を渡す側にとっては、金額が大きくなるため少し負担に感じることもあるかもしれない。だから、その子との関係や他の兄弟姉妹とのバランスを考えて、金額を決めることが大事だよ。
小学生や高校生の兄弟姉妹とは差をつけることが良いかもしれないけど、中学生が二人いる場合は、同じ金額を渡しても大丈夫だよ。
高校生の場合
高校生の場合も、中学生と同様に5000円から1万円が一般的なお年玉の相場。
でも、高校生になるとお金を使う機会がさらに増えて、バイトを始める子も多いんだ。
この時期は、お金の使い道や金銭感覚について、家庭ごとに考え方が異なることもあるよ。
だから、お年玉の相場に固執しすぎず、渡す側の判断で金額を決めるのがいいかもしれないね。
1万円以上を渡す場合は、現金に加えて5000円分の図書カードを添えるなど、工夫するのも一つの方法だよ。
勉強や読書に役立つものを選べば、相手の親も喜んでくれるし、お互いに気を使い過ぎることも少なくなるはずだよ。
大学生・専門学生
お年玉に関するQ&A